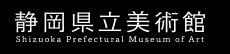![]()
開館25周年を迎えて
江戸・東京に咲きひらいた絵画 ―とくに鏑木清方の《讃春》(前編)
芳賀 徹
静岡県立美術館がついに開館25周年を迎えた。まことにめでたい。24周年目から館長となった私としては、長くこの館の活動を支え励まして下さった県民、市民の皆さまにあらためて感謝の念をささげ、初代鈴木敬先生以来の代々の先輩館長と館職員諸氏が力をあわせてこの館の名声を高めてきてくれたことに、深い敬意をあらわす以外にない。
25周年を記念して「芸術の花ひらく都市」展が開催される。これを機に、わが足もとの江戸・東京の美術史的一側面をうかがってみよう。
司馬江漢の銅版画《三囲景図(みめぐりけいず) 》、《不忍池図》、《中州夕涼図》、あるいは私の大好きな《広尾親父茶屋図》などに始まって、大都市江戸も世界有数の「藝術の花ひらく都市」としてみずからの絵姿をもつにいたった。北斎の『富嶽三十六景』のなかの富士の見える江戸のすがたや、最幕末の広重の『名所江戸百景』も、江漢に続いて江戸の四季の風流とそのなかに生きるよろこびとを讃えた合唱曲であり、やがて終わろうとする「徳川の平和」(パクス・トクガワーナ)に捧げられた美しい挽歌でもあった。
新興の政治都市であった江戸も、その250余年の平和の歴史の間に、都市風景の浮世絵というこの都市ならではの表現様式を生みだし、都市と美術の間に相互触発・相互美化の関係を成り立たせるに至った、といえるのだろう。
その江戸が東京となって、日本の近代化=西洋化を急速に首導する立場に立つことになると、江戸までの都市景観と絵画の間の調和はにわかに乱れはじめた。市街の風景も、それを描こうとする画家たちの画材や画法も、それぞれちぐはぐに西洋をとり入れて自己展開するようになったからである。それでも、新首都東京のあわただしい変貌それ自体に興味をそそられて、新しい景観と新画法との間を軽わざのようにしてでも結びつけて、新しい生活風景を表現しようと試みる画家は、明治から大正、昭和にかけてつぎつぎに登場してきた。
明治の洋画科高橋由一や版画家小林清親から、大正の岸田劉生や木版画の川瀬巴水、また資生堂のデザイナーたち、そして戦前戦中昭和の佐伯祐三や長谷川利行や松本竣介らの油彩、また木村荘八のペン画挿絵にいたるまで、私はいまから20年ほど前、近代の画家たちの東京風景領略の試みの跡を、彼らの作品に即して探ってみたことがあった(拙著『絵のなかの東京』、岩波書店、1993年)。そして、彼らの描く陰翳に富んで、たえず「普請中」の不安にゆれ動く、埃っぽくて元気でなにか物悲しい東京の絵姿こそ、同時代の画家たちの好んで描いたパリやロンドンの名所絵などよりも、実ははるかに面白く、絵としてもすぐれているのではないか、と思った。また幾たびもの戦争や災害をくぐりぬけてきた近代都市東京の歴史の、同時代文学作品にも劣らぬ生き証人となっているのではないか、とも考えた。
東京を描いたこの近代画家たちのなかに、いわゆる「日本画」の画家はめったに登場しなかったし、そのこと自体、近代日本画の一つの特徴を明示していたのかもしれない。だが、一人例外の画家がいた。それが鏑木清方だ。(続く)
(はがとおる 当館館長)