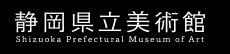![]()
江戸・東京に咲きひらいた絵画
―とくに鏑木清方の《讃春》
芳賀 徹
築地や木挽町という下町で育った鏑木清方が、誰よりも古きよき東京に強い愛着をもち、生涯にわたって郷愁を抱きつづけたことは、彼自身の幾多の文章によっても広く知られている。ごく若いときの《佃島の秋》(1904)や樋口一葉『たけくらべ』の挿絵風連作(1896)に始まって、天下の名品《築地明石町》の美人画(1927)や戦後の『朝ちょう夕せき安あ ん居き ょ』(1948)にいたるまで、清方には近代の東京風俗を描いてこの上もなく美しくなつかしい作品が多い。
そのなかでもとくに忘れ難いのは《讃春》と題された六曲一双の屏風絵だ。昭和天皇の即位礼を祝して、昭和8年、岩崎家から宮中に献上された5人の日本画家の屏風絵の一つだという。私はこれを1982年の東京小田急の清方展ではじめて見て感銘を受け、1999年の東京国立近代美術館で再度これに接した。戦前昭和の東京の明と暗を、どちらももっとも美しく描ききった名作である。
右隻には、向こうの柳と石垣の上に宮城(皇居)を望む広場の土手に、黄色いたんぽぽの混じる芝草を踏んで黒いセーラー服の女学生二人。一人は制帽をかぶり、後ろ手をついて草の上に長々と脚をのばし、立ったままのもう一人となにか話している。土手の松の向こうには黒い自動車が一台。やがて戦時下となれば軍部から不敬のおとがめを蒙りかねない大らかな山の手の春ののどかさだ。
そして左隻は一変して、薄い胡粉の春の靄のなかの清州橋を背景に、隅田川畔の水上生活者の母娘の情景。舫(もや)い船の狭い船倉の屋根が開いていて、中から見上げる母と屋根の上の赤い着物のおかっぱの女の子が、これもなにか話している。つつましいこの母娘の船の舳先には、手桶に満開の桜の一枝が飾られ、ともの方には鉢植えの花。隣の舟の船ばたには七輪の火が薄青い煙をあげ、画面右手には都鳥が一羽飛び立っている。右隻の皇城とブルジョア女学生ののどやかさに対し、左隻はまたなんと「もののあはれ」の味わい深い下層民的風流であろう。
「藝術の花ひらく都市」展というとき、鏑木清方のこの屏風一双も忘れ難く、これこそ昭和東京に咲きひらいた大輪の花の一つにちがいないと思いおこし、ここに言葉によって追加展示をこころみた。
(はが とおる 当館館長)
鏑木清方《讃春》1933(昭和8)年 六曲一双 絹本着色 各隻202×438cm 宮内庁三の丸尚蔵館
※この作品については、以下のカタログ等をご参照ください。
『新版 雅・美・巧 所蔵名品300選』(下) 宮内庁三の丸尚蔵館 2003年