
平成14年度夏休み子どもワークショップ
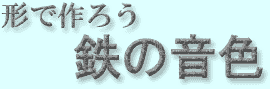
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

平成14年度夏休み子どもワークショップ
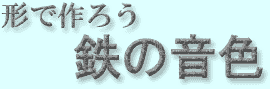
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 実技室プログラム
実技室プログラム
 講演会・美術講座
講演会・美術講座
 学校向け普及事業
学校向け普及事業

 ギャラリートーク
ギャラリートーク
 移動美術展
移動美術展
 ロダン館まめちしき
ロダン館まめちしき

|
 TOP
MENU
TOP
MENU 
 Copyright
(c) 1997-2001 Shizuoka Prefectural Museum of Art
Copyright
(c) 1997-2001 Shizuoka Prefectural Museum of Art