|
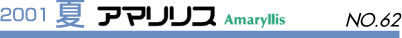
研究ノート
ロダンは浮世絵をどう見たか
飯田 真
静岡県立美術館で開館15周年記念展として開催された「ロダンと日本」展(註1)は、ロダンと日本の関係をさまざまな角度から再検証した展覧会で多方面から注目を集めた。中でも浮世絵を中心としたロダンの日本美術コレクションの展示は、一般来館者の人気を博しただけでなく、ロダン研究、ジャポニスム研究の上で新たな材料の提示となった。今後、さらなる研究の進展が期待される。また、今回、ロダンのコレクションのひとつとして、ファン・ゴッホ《タンギー爺さん》とその背景を飾る浮世絵の原典が特別出品されたこともあり、西洋と浮世絵の関係を再び考えるよい機会となった。
ロダンと浮世絵の関係については、同展図録のクローディ・ジュドラン氏と神谷浩氏の論考を参照いただきたいが、実際に作品が展示されたのを契機に、ロダンが浮世絵をどのように見たか。どのように芸術に取り入れたのか。あるいは西洋でもてはやされた浮世絵とは何だったのか。という簡単には解き明かせない大きな問題をあらためて整理しておきたい。
ロダンが活躍した19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパはジャポニスム流行の渦中にあり、とくに芸術家は日本を意識しないではいられない時代であった。それはちょうど明治期の日本の芸術家が西洋を意識しないではいられなかった状況の裏返しであるともいえよう。そうした状況の中、ロダンは日本美術とりわけ浮世絵に興味をもち、作品を収集したわけであるが、実際の浮世絵作品をロダンがどう見たか。今回展示されたコレクションの具体的な作品に即して検証していこう。
『惠斎麁画』(北尾政美画・図1)は浮世絵師から津島藩のお抱え絵師になった異色の画家・北尾政美(鍬形惠斎)の手になる絵本で、略筆(草体)で描いた人物・草花・風景・魚虫などを種類ごとに分類して収めた作品である。森羅万象を描き尽くす態度、略画による絵手本という趣向など、『北斎漫画』の源流となったものとされる。『北斎漫画』が早い段階からヨーロッパで高く評価されたことはよく知られるが、ロダンが『北斎漫画』に近いこの作品に興味をおぼえたのは想像に難くない。簡単な線だけによる素早い描法によって、人間を含めた自然界が生き生きと描かれていることに驚嘆したことであろう。またモチーフの採り方にしても、西洋流に構えたところが全くなく、日常生活でよく見かける実に平俗な光景であることも印象的であったに違いない。本作品とロダン作品との関係は、素描によくあらわれている。すなわち、ロダンが素描において極力無駄を廃した省略された線だけで、対象の動きやそれを含む本質を描いたこと。また、手元を見ずにモデルだけを見て素早く描いたという手法、あるいはモデルを静止した姿勢で描かなかったことなど、こうした作品との関係が指摘できよう。
喜多川歌麿《当時全盛美人揃 玉屋内小紫 こてふ はる次》(図2)は、『白樺』同人が贈った作品のひとつであることが、今回の展覧会でロダン美術館により明らかにされた作品であるが、歌麿全盛期の作で、当時の名高い遊女の姿を描いた揃物のひとつ。蔦屋重三郎の企画で大当たりをとった大首美人画の形式を継承し、優麗で安定した歌麿様式をもつ作品で、ゆったりとしたポーズをとった女性を画面の片側に寄せながら、女性の視線や小道具を用いて、落ち着きの中にアクセントとなる動きを出している。また余白の黄潰しが着物の著彩と調和を見せることも本図の見どころとなっている。なお、1911年、与謝野鉄幹・晶子夫妻がロダンを訪れた際、土産として歌麿の版画を贈ったこと、そしてロダンが歌麿の絵を眺めて「彫塑の行方と似た行方をしている」と評したことが日本側の資料にのこされており、その意味でもロダンが歌麿をどう見たかは興味深い。
まず本作品でも、優雅な女性の微妙なポーズを描く重要な要素が「線」であることに注目したい。西洋画と比較すれば、本図が例えば皮膚の質感や、着物の質感などが再現されていないのは明らかである。しかし、「線」を中心にした簡素な表現ながら、そこに女性の身体のしなやかさや、そこから発する色香が見事に表現されていることにロダンは注目したに違いない。西洋の概念では、簡略とも思える表現にもかかわらず、その本質を的確に捉えている点に、「彫塑の行方と似た行方をしている」の真意があるものと考えたい。
一方、歌川豊国《役者舞台之姿絵 はまむらや》(図3)も『白樺』同人寄贈作品であるが、本作は役者の決めのポーズを画面一杯に描く役者絵である。全身像であるため彫刻との関連が想像される。ここでは簡素な線描とともに、単純な人物のフォルムに注目したい。日本の着物の形態とも関係するが、すっと立った人物の形が単純に表現されながら、かえってその存在感が誇張されている。まさにこの点にロダンの彫刻との関連がうかがえる。この人物のポーズを見て思い出されるロダン作品は、その代表作である《バルザック像》であろう。試行錯誤の末、最終的にガウンをまとった姿で表現された《バルザック像》は、無駄な細部を捨て去った、極限まで単純化された形態のシルエットに特徴があり、モニュメンタルな力強さをもっている。《バルザック像》がサロンに出品されたのは1898年で、『白樺』同人が浮世絵を贈った1911年以前のことであるので、もちろん、《バルザック像》が本作からの影響であることは在り得ない。しかし、ロダンが本作を見て自らの芸術との関連で共感を覚えたことは容易に想像できよう。ロダンが浮世絵に自らが目指す芸術の方向性において共感を覚え、賛辞を寄せていたことは、こうした作品とロダン作品との対比によってより明確に理解されるであろう。
以上、ロダンが浮世絵をどのように見たか、自らが所蔵した具体的な浮世絵作品に即して述べた。しかし、これらはロダンと浮世絵との関係の一部をしめすにすぎない。先にも述べたとおり、ロダンが活躍した時期はジャポニスムが盛んな時期で、かなりの情報が早い段階でロダン周辺にすでに広まっていたと思われる。したがって印象派の場合の直接的な影響関係とは異なり、ロダンの場合はその潜在的な意識の中に浮世絵の造形が植え付けられていたのであろう。それがさまざまな形でロダンの反アカデミズムの方向と合致したものと考えたい。したがって、ロダンは、浮世絵に対し自らの芸術との共感を込めた賛辞をおくったのである。
(当館主任学芸員)
|

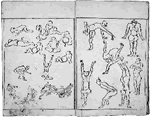
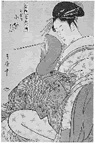
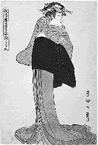
 来館者の声
来館者の声
 Copyright (c) 2001 Shizuoka Prefectural Museum of Art
Copyright (c) 2001 Shizuoka Prefectural Museum of Art