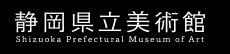![]()
研究ノート
フランソワ・ブーシェの〈洗濯女〉の描写をめぐる一考察
小針由紀隆
19世紀後半、パリの市民社会が爛熟するにつれて、洗濯女、踊り子,音楽家,競馬,浴女,カフェなどは、画家や小説家の取り上げる題材として着実に注目の度を増していた。美術批評家のエドモン・ド・ゴンクールは、1867年に出版した小説『マネット・サロモン』の中で、洗濯女と踊り子がもっとも絵になる当世風のモデルを芸術家たちに提供すると述べている。
エミール・ゾラが小説『居酒屋』を発表して話題をさらったのも、その10年後であった。ゾラのこの小説は、南仏の田舎からパリに出てきた若い女が、持ち前の負けん気と生活力で洗濯屋を開くが、次第に酒と愛欲の魔力に取りつかれ、やがて堕落と破滅に向かっていくさまを描いている。作者は大都会における労働者の典型として洗濯女を選び出し、その実態を冷徹に観察しながら、人間の破滅に向かうパターンを暴きだそうとしている。そうした意図をもつゾラにとって、洗濯女は格好の階級と職業だったのだろう。
小説だけでなく絵画にも目を向けてみよう。19世紀後半になると、絵画でも低俗で気品を欠く主題がよく選ばれるが、洗濯女はその最たるものと見られていた。先にあげたゴンクールの記述を鮮やかに実践した画家は、エドガー・ドガであった。ドガは庶民の仕事ぶりに強い関心を示し、1869年から1896年まで洗濯女にモティーフを求めつづけた。といっても樽やタライを用いての洗濯ではなく、その労働はアイロンがけやリネン運びとなっている。実例をあげてみよう。
1884年の《アイロンをかける女たち》(オルセー美術館、図1)は、もっとも注目に値する作品である。作業台に立つ二人の女は、ひたすらアイロンがけを繰り返しているようで、一人は疲労と倦怠から大きな欠伸をし、もう一人は両手を合わせアイロンに力をこめている。ドガはパリのどこかの洗濯屋に立ち入り、その作業場にもっとも現代的なモデルを見出していた。疲れと肩こりに耐える洗濯女の身振りと表情は、ボードレールの言う一時的なもの、移ろいゆくもの、偶発的なもの、すなわち「現代性modernité」をよく映している。
独立した絵画主題としての洗濯女の作例、それも顔の表情が描写されている作例は、19世紀以前のフランス絵画からも探し出すことができる。ジャン=バティスト・グルーズが1761年のパリのサロンに出品した《洗濯女》(ポール・ゲッティ美術館、図2)はその好例である。このカンヴァス画は小さいながら、バラ色の頬をもつ少女のふくよかさと生彩にとんだ色彩が多くの批評家たちの目を惹きつけていた。たとえば美術批評家のディドロは「洗面器にかがみこみ、衣類を揉み洗いしているこの小さな洗濯娘には心を動かされる。しかし少しも信用できそうもない奴だ。この家にあるあらゆる家庭用具には深い真実が感じ取れるが。」と評し、彼女のずるがしこそうな眼差しと事物の描写の精巧さを併せて指摘している。同じ18世紀のシャルダンの風俗画から強い刺激をうける一方で、グルーズは当時のパリで知られていた17世紀オランダの風俗画、たとえばハブリエル・メッツのような洗濯女の作例を学んでいたのかもしれない。
グルーズの《洗濯女》とほぼ同時期に描かれた作品に、フランソワ・ブーシェの対をなす風景画がある。1764年の年記をもつこれら2点(静岡県立美術館、図3)は、それぞれ朝と夕方の風景となっているが、両作品とも前景に仕事に励む洗濯女が配されている。前かがみになって汚れ物を洗う彼女たちは、白と朱色の衣服によって鑑賞者に強い視覚的印象を与えている。ブーシェは洗濯女の瞬時的心情を扱うのではなく、彼女たちを装飾的な点景として描きいれている。のどかで喧噪のない田舎での営みに、生きる苦しみは感じ取れない。画面全体を満たしているのは、田舎の静けさと安らぎに他ならない。この村は愉しく生きるために必要なものが何でも揃っている小世界、都会であくせく働く人たちが羨むような悦楽の世界なのである。

図1 ドガ《アイロンをかける女たち》
1884年 オルセー美術館

図2 グルーズ《洗濯女》
1761年 ポール・ゲッティ美術館

図3 ブーシェ《石橋のある風景》
1764年 静岡県立美術館
フランス、とくにパリの洗濯女たちは、ギルドや協同組合を組織していたわけではないが、15世紀以来ひとつの職業とみなされ、その仕事の内容は17、18世紀を通して基本的には大きく変化しなかった。現存するいくつかの絵画——たとえば1786年のユベール・ロベールのカンヴァス画——が視覚的ドキュメントとなるように、セーヌ川沿いの或る地区では洗濯女たちの集団が船上で洗い物をしていた。そのありさまは品格を欠く集団の風景であり、店舗を構えてのクリーニング業とも趣を異にしている。
図版で紹介できないのは残念だが、ブーシェ時代のフランス絵画には洗濯女のさまざまな描写が散見される。1756年から60年まで、ローマに滞在したジャン・オノレ・フラゴナールは、ティヴォリを散策しながら、高低さのある幾つもの眺めをチョークと油彩で描いていた。ルーヴルにある油彩による《ティヴォリの大瀑布》は、生活臭を漂わせる洗濯女たちを伴うフラゴナールらしい作品となっている。この《ティヴォリの大瀑布》が、かつてユベール・ロベールの作と信じられていたことは興味深い。1754年から11年以上イタリアで活動したロベールも、フラゴナール同様、ティヴォリの風景を気ままに描いていて、そうした作品の中には貧しい庶民の姿を交えたものがいくつもあった。マリオ・プラーツに言わせれば、ロベールの好んだ洗濯女のモティーフは、理想化されたローマの風景に加えられた「香辛料」だったのである。
とはいえロベールは洗濯女をいつも点景として扱っていたわけではなかった。壮大な遺跡のなかの小さな添え物としてではなく、中心的モティーフとして取り上げた作品も描いている。やはりローマ滞在中の作である《洗濯女と子供》(マサチューセッツ、ウィリアムスタウン美術館)では、ひもに白いシーツを干している女とその隣で用をたしている男児が比較的大きく配されている。このように洗濯女は大きさを変えながら、ロベールやフラゴナールの作品に登場していた。
ここまで見てきた洗濯女の描写を伴う作例は、ポンパドゥール侯爵夫人とブーシェによって盛期をむかえたルイ15世の治世、大革命以前のフランスで制作されている。装飾の過剰、官能の解放、遊戯の尊重、表面的な軽薄さ——こういった諸要素はロココ文化の特色としてよく指摘されるが、ディドロがそうだったように、これらはブーシェの絵画を批判する際の常套句でもあった。ディドロによるブーシェ批判は1765年からより痛烈なものになるが、しかし裏を返せば、それまでは人間が自らの欲望に任せ、人間らしく愉しく生きようとした時代であったと言えよう。
ブーシェは1740年代から洗濯女に関心を抱き、幾度も風景画に描き込んでいる。時には対をなす2作品に、洗濯女と釣りをする女を選んでいる。この画家は、洗濯女の労働と、釣りをする女の遊びとを対比させているのではなく、戸外での洗濯も釣りと同じく、気晴らしとなる営みと考えていたのだろう。ブーシェが描こうとしていたのは、人々をやさしく包み込む自然であり、古代以来ヨーロッパ文学の世界を流れる「心地よき場所 locus amoenus」のトポスにつらなるものであった。
ホメロス、テオクリトス、ウェルギリウスらによって形成された「心地よき場所」のトポスには、樹木、草地、水もしくは泉が欠かせなかった。そしてそこに遊ぶのは閑暇のある牧人たちであった。ブーシェの風景画がこのトポスにつらなるとすれば、洗濯女も「心地よき場所」にすべりこんできたことになる。——洗濯女の描写の歴史をたどる研究は、理想郷における労働という問題を含め、さまざまな検討材料を提供する興味深いテーマといえよう。
(こはり ゆきたか 当館学芸部長)