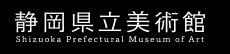![]()
研究ノート
菅井汲の求めた表現とその変遷について
菅井汲は、兵庫県出身ながら夫人が広島市出身の縁により、2008年、遺族からまとまった数の作品が広島県立美術館に寄贈されている。そのため菅井汲は、広島県立美術館のコレクションの中でも大きな位置を占めているが、菅井が最晩年アトリエを築いた地が静岡県であり、また、静岡県立美術館には菅井の代表作《MasseNoir(黒い塊)》が収蔵されている。静岡県立美術館と広島県立美術館が相互協力協定を締結した今年は、静岡、広島両県に関わりのあるこの作家について見直してみる良い機会ではないかと考えた。
菅井はその波瀾万丈の人生で、様々な事件をきっかけに大きく作風を変化させているのだが、その根底には絶えず一定の方向性があったように思われる。
様々に変化する作品から、菅井の内面にあったであろう表現への指向性を整理してみたいと思う。
先に挙げた《黒い塊》という作品は、菅井汲が1965年のサンパウロ国際ビエンナーレで外国作家最優秀賞を受賞した際に出品した16点の中の一つで作家初期の出世作だが、何かのポスターに使っても良いくらいデザイン的な要素の強い作品だ。こうした作品を見るたびに気になるのが、菅井が求める美術の姿とはどういうものであったかということである。
菅井は渡仏する以前の1937年から1949年まで阪急電鉄(阪神急行電鉄株式会社事業部)宣伝課に勤め、ポスター等のデザインを行っていた。宣伝美術の専門誌「プレスアルト」などの記事から当時の菅井の活躍を知ることができる。またこの頃、日本画に興味を持ち、中村貞以に弟子入りしたこともある。1年ほどで中村の門を離れたが、日本美術院再興第34回展に《塩造る家々》が入選するなど、かなり本格的に取り組んでいるし、渡仏前後まで紙に岩絵の具を使った作品の発表を続けている。同時に、「具体」を立ち上げる直前の吉原治良にも指導を受け二科展に出品するなど、油彩画にも相当なエネルギーを注いでいたことが判る。このように様々な技法を学びながら自らの表現を模索していた菅井だが、団体展を重視する日本にいては作品で勝負するのは難しいと考えるようになり、海外留学を検討するのだが、毎日新聞に掲載された出発前のインタビューには「出来れば二年位滞在して生涯の仕事であるシュールレアリズムとアブストラクトをくっつけた仕事を日本画に如何に表現するかを追求し」また「海外生活を通じて日本人のよさを再認識し」たい、などと語っていて、まだ、比較的短期間海外に出て日本画的な表現を追求しようとしていたことが伺える。渡仏後の菅井は、結果として油彩画を基本にすることになったが、シュルレアリスム的な要素を含んだ抽象絵画を日本的な感性で表現して評価を受けたわけだから、その意味では出発前に望んでいた成果を得たとも言えるだろうか。

菅井 汲《Masse Noire》
1964年(昭和39年)
油彩、キャンバス
195.0×130.0㎝ 当館蔵

菅井 汲《NATIONAL ROUTE》
1964年(昭和39年)
油彩、キャンバス、195.0×130.0㎝
広島県立美術館蔵
※同じ海坊主型の作品だが、広島のものには、まだマチエールが残っている。
パリで生活するようになってからの菅井は、象形文字ともとれるイメージを繊細なマチエールで描き上げて、たちまちパリを代表する人気作家となった。その彼が60年代初頭、色面構成的な作品を描くようになると、それまでの菅井の支持者は徐々に菅井から離れていく。それでも菅井は人気のことなど意に介さずこの新しい表現を推し進めていくわけだが、こうしたところからもデザイン的な表現を求める菅井の指向性が垣間見えるように思う。60年代後半、菅井はそうしたデザイン感覚を存分に発揮して、自ら「自信のある形」と称する基本形態を生み出し、その形を様々に展開して新しい作品を生み出していく。この基本形態を繰り返し描く手法は、たとえば「海坊主型」やL形を繰り返し組み合わせたバリエーション。「S」と呼んでいた洋弓型のバリエーション、さらには基本形態を使った立体作品など、枚挙にいとまがない。

菅井のアトリエ 2003年角田撮影
渡仏して間もなく繊細なマチエールで一定の評価を受けた菅井が、わずか数年後の60年代なかばには、肝心のマチエールを排除してしまった理由については様々な説が存在するが有力なのは次の二つ。一つ目が、人気が出たためそれまでの手法では注文に応じきれいという技術的な問題だったとする説。二つ目は、油絵同様に力を注いでいた版画では、油絵のようなマチエールを表現できないため、版画用にマチエールが無くても面白い画面を研究するうちに、油絵もマチエールに依存しないまま面白い画面作りが可能になったのだという説。しかし、できるようになったからやるかといえばそうではないはずだ。つまり、そうした仕事を通して、表現の方向性として、もっと整理された画面、記号的な表現を、彼自身が指向していたことを再認識したのではないだろうか。
こうしたマチエールの排除について菅井は、一つ一つの作品に力を注ぎ込むことは「コレクターを喜ばせるだけ」と、切って捨てているが、後に、作品には機能があるべきだと考えるようになる菅井であれば、そうした方向性へのアプローチが既に始まっていたと考えることもできる。菅井はその後も「自信のある形」を組み合わせたり、単独で描いたりしながら、図案的な表現で力強さを追求していく。菅井は1960年代の終盤から「絵画の機能」ということをよく口にし、未来の美術を創出することに熱中したが、何年かの後、自分の年齢を考え、「残り時間」を意識するようになったという。新しい美術を切り拓くには時間が足りない。そう思ったら、若い頃に我慢して切り捨てたマチエールを楽しむ絵画に戻りたくなったのだと。1880年代、洋弓型の図形にマチエールが盛り込まれた「S」のシリーズなどを作った時期がそれだ。しかし結局、菅井はこの表現にも満足できず、90年代に入るとマチエールをまったく伴わないカドミウムレッドのシリーズに取り組み、明快で力強い図案的な作品を深化させていく。
このように最晩年まで続く菅井の創作スタイルの変遷は、絵画の機能という考え方や、マルチプルの作品制作同様、初期にデザイナーとして活躍した菅井の資質と無縁ではなく、素朴な質感にも原初的な好感を抱きつつ、デザイン的なシンプルさに知的な美のあり方を求めた菅井の生き方そのものの投影だったように思われる。
さて、最後になったが、菅井が日本に造ったアトリエについて触れておきたい。菅井は他界するまでに合計7度帰国しているが、その都度、新しい表現への手掛かりを見つけたようだ。そんな菅井が日本にいる間、もっとも不満に感じていたことが制作の拠点がないことだった。その不満を解消するため菅井は帰国するたびに仕事場を探した。最初は山口県の萩市沖合に小島を買い取り独立国を作ろうと考えた。さすがにこれは実現しなかったが、その後もあきらめることなく適当な制作拠点を探し続けた。そして最終的に菅井がアトリエを建てたのは、静岡県熱海市だった。先にも述べたように、日本へ帰国中に開催する個展や展覧会の合間、もてあます時間を有効に使うためと、創作へのヒントを逃すことなく、すばやく作品として定着するためだったが、将来的には日本へ帰ってくることも意識していたかもしれない。建物は新築で、当然近代的なものなのだが、パリのアトリエを意識したといい、創作を中心に設計されている。総2階建ての建物は、採光を考えてのことだろうが2階は全てメインのアトリエとなっていて、天井は高く、大部分が採光のためガラス張りとなっている。版画のアトリエは1階で、廊下からは愛車ポルシェが見える。
また、有名な温泉保養地だけあって、ここには温泉がひいてあり、自宅で湯治ができた。
残念ながら菅井はこのアトリエを十分に活用することなく世を去ってしまったが、菅井が、このアトリエで制作に取り組んでいたらどんな作品を世に送り出していたのだろうかと想像が膨らむ。静岡とも縁薄からぬ作家である。
角田 新(当館上席学芸員)