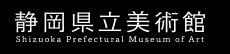![]()
美術館問はず語り
画家とその妻 −「宮芳平自伝」(未刊行)より
女房は死んだ。感傷になるかもしれないが許していただきたい。蓮の花が咲いていた。わたしは一茎を折って瓶に挿した。医者を呼んでの帰りである。瓶に挿された花は枕元に置かれた。白い花であった。医者が来た。女房が言った。「先生、早く楽にして下さい。」「ああ、すぐ楽にしてあげるよ。」(中略)女房の瞼がまばたきするようにふるえた。間もなく静かになった。たとえようもない静かさである。そして枕元の蓮の花が一ひら落ちた。ぽたりと。
わたしは女房が「信仰を得た平安」に死んだとは思わない。わたしは女房の死期が近づいたことを知った。医者もそのことを暗にわたしに告げた。女房もやがてみずからでそれを知った。その時の女房の孤独感と絶望、それは見る眼もあわれであった。女房が若しもわたしのほんとうの恋女房であるならば、わたしは女房と共に死ぬべきであった。
『AYUMI』32号 昭和39年12月発行
わたしの女房が死ぬ時/わたしの女房は信仰にはいれなかった/はいったとみた信仰がはいっていなかった/あの苦しみ、あの未練/死期が近づいた時、そうと自分で知覚した時/忍従の中に沈黙していた怒りが/怨言となって噴き出した/それでもとうとうこう言った/「お医者様、早く楽にして下さい。」/「ああ、楽にして上げるよ。」/そして彼女は死んでいった
『AYUMI』3号 昭和36年6月発行
宮芳平(明治26〜昭和46年)は、森鴎外の短編小説「天寵」のモデルになった画家。中村彝に師事し、曽宮一念とは生涯の交友を結ぶ。長野県諏訪の女学校に嘱託の美術教師として赴任、無名だが朴訥な画業を送った。宮の自伝は、退職後、女学校の教え子たちへ送られた。わら半紙にガリ版刷りの手製雑誌だった。自伝の基底にあるのは、戦時中に亡くした妻エン(享年47歳)への自責の念である。純粋ゆえに稼ぎのない画家と、その画家を支え続けた妻。教え子たちに妻の人生を語ることは、女性の生きる苦しみを諭すとともに、若者たちの無垢さを前にした自らの懺悔でもあったのだろう。
作家が生きることの辛さと、作家を支える者の辛さ。それは、いつの世も変わらない。今の若い作家とその伴侶や支援者と語るとき、私の脳裏には宮芳平とその妻が思い起こされる。恨み言の裏にも、固い心の絆があったにちがいないと信じつつ。
(当館主任学芸員 堀切正人)