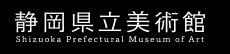![]()
遠くて近かった古代エジプト
「トリノ・エジプト展」が8月22日の日曜日に終了した。6月12日に始まって、62日間の会期中に13万7千余名の入館者があったというから、大変な人気だった。ロダン館開館記念展のときの、87日間に14万674名という記録に次ぐ当館史上二位の数となったのだから、まことにめでたい。
私自身も、会期中になんべんとなく会場をうろうろして、展示を見直してはたのしみ、来館者たちの感嘆の声やささやきや好奇心いっぱいの眼ざしに接しては、心からよろこんだ。老若男女さまざまの人々が、息を呑むようにして作品に魅せられているのを見ることほど、主催館の館長としてうれしいことはないのである。
「死者の旅立ち」の室などでは、ミイラの棺の内部の絵模様をよく見ようとしてか、アクリルの大きなケースに頭をごつんとぶつける音をなんどか聞いた。実は私自身も、包帯を巻きつけられた男性ミイラのなまなましい脂のにじみ跡などを見つめるうちに、あやうく頭をぶっつけそうになった。こういう薄気味悪いほどのなまなましさ、三千年、四千年昔の人が今ここに眠っているという不思議さの迫力も、今回の展示の大いなる魅力で、その魅力に惹かれて思わずアクリルに頭をぶっつけてしまうのは、私をも含めて、中高年の男性に多いようだった。
それにしてもエジプト展はなぜこれほどに日本の老若男女の心を惹きつけるのだろうか。七年前に当館で「古代エジプト文明展」が催されたときも、ひと月の会期で11万6千人の入場者があったというから、ただごとではない。古代エジプトといえば、日本からは地理的にも時間的にも、おそらく人種的にも、もっとも遠く離れた文明のはずではないか。紀元前三千年から始まるというエジプトの王朝や王の名前などは、ツタンカーメンやプトレマイオスなどを除けば、みななじみが薄く、私などなんど年表を見てもおぼえられない。
遠い異質の文明であるだけに、いっそう私たちの未知への好奇心をそそるのだろう。頭のなかにピラミッドやスフィンクスの巨大で神秘な映像がすぐに浮かんで、心を掻き立てるのでもあろう。そして実際に会場に来てみると、古代エジプトの彫像も器物もミイラの棺も、意外なほどに私たちの感覚に親しみ深く、三千年の距離を一挙に越えてなまなましく迫ってくる力をもっている。そのこと自体に私たちはあらためて驚くのだ。
エントランスホールの階段わきにおかれていた《オシリス神をかたどった王の頭部像》などは、すでに当館友の会会報(『プロムナード』)でも触れたが、それを見たとたん私は「あ、エジプトの阿修羅!」と叫んだものだった。それほどに、あの大きな眼を見ひらいて頬笑みを浮かべた若い王の面ざしは美しく気品があった。アメン神の肩に右手を廻すツタンカーメン王の石像も、なんと颯爽として若々しく、聡明さと勇気とを感じさせることか。みごとな表現力で、王は今なお私たちに向かって進み出てくるかの気配だ。昨年冬に西洋美術館で見た「古代ローマの遺産展」の石像群などよりはるかに私たちに身近で、語りかけてくる言葉さえ通じそうにも思われた。人型棺の顔には、日本の能面の源流はここにあるかと思い、いくつもの大きな人型棺の蓋の、手足のない像は、ロシアの人形マトリューシカや日本のこけしをすぐに連想させた。
こういう発見や連想はまことにたのしい。私たちの世界像をぐいぐいと押しひろげ、想像力にさかんな活力を与えてくれる。そして終わりにもう一つ。横に長い《死者の書》は、上欄に絵模様を入れた上で、縦に罫を引き、そこに縦書きでヒエログリフの文章を書きこんでいた。まるで夏目漱石の専用用紙に書かれた「道草」かなにかの原稿のようだったのである。
(当館館長 芳賀 徹)