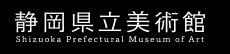![]()
研究ノート
曽宮一念《毛無連峯》に関する一試論 〜「もうひとつの絶筆」をめぐって〜
泰井 良
はじめに
曽宮一念《毛無連峯》(昭和45年(1970) キャンヴァス・油彩 静岡県立美術館蔵図1)は、これまで彼の絶筆とされてきた。ところが、最近、曽宮夕見氏(曽宮一念令嬢)の証言によって、本作以後に制作された同じ主題の作品《失題 毛無山》(昭和45年(1970)以降 キャンヴァス・油彩 個人蔵図2)があることが判明した。本作品は、曽宮一念の没後、今日に至るまで、曽宮夕見氏の手元にあった作品であり、出品・文献歴等のない新出作品である。
本稿では、《失題 毛無山》と当館所蔵作品《毛無連峯》とを比較しながら、曽宮一念にとっての絶筆の意味、さらには彼の風景画制作に対する姿勢について試論を述べることとしたい。
1.《毛無連峯》について
曽宮一念のご遺族である曽宮夕見氏は、《失題毛無山》が、絶筆とされてきた当館所蔵作《毛無連峯》の制作後に描かれた作品であると語った。当館所蔵作に比べて、《失題 毛無山》は、寸法は小さく、また作品の仕上げという点から、その完成度は当館所蔵作には及ばない。しかしながら、画面に見られる極太の描線や荒々しい筆致、大胆な色彩表現は、画家の内面的な感情を吐露するかのように表現的で力強い。本人も語っているように、当館所蔵作が制作された頃、曽宮の視力は、皆無に等しかったので、その後に制作された《失題 毛無山》は、ほとんど「記憶」を頼りに描かれたことが窺い知れる。そして本作が、そのような状況の中で制作されたとすれば、《失題 毛無山》の曽宮の画業における意義は、極めて重要であるといえる。
さて、当館所蔵作品は、これまで曽宮の絶筆であるとされてきた。そのことは、曽宮のつぎの発言によって裏付けられる。
「ひとつはアトリエから窓のほうを眺めるとよく見えた毛無山を描いたもの。もう視力がありませんでしたから想像で描きました。二十号の油絵で、絶筆ともいえる『毛無連峰』です。これは毛無山を描いたもののなかで一番出来がいいものです。」1
曽宮が制作した毛無山を主題とする作品は、確認できるものだけで、先の2点を含めて、《毛無連峯》(昭和39年 キャンヴァス・油彩33×53cm)、《毛無連峰》(昭和43年油彩 90.9×65.2cm)と4点である。また、その他、《毛無山と天子岳》(昭和34年紙・鉛筆)などスケッチ類も多く残されている。曽宮は、毛無山について、「西の方には毛無山がある。これも富士の裾に毛無連峯っていって小さい山がいくつも続いて見える。そばに行くと、実際は離れているんですけどね。これは一番冬がいいですよ。頂きに雪も降るし、霧氷がしっかり山を真っ白に飾りまして、その朝早く、非常に寒いんですけど、二月の初めくらいがいいですね。」2 と語っており、いずれの作品も曽宮のアトリエから窓越しに毛無山を遠望したものである。画面のおよそ三分の一の位置に地平線を配し、それに沿って毛無山を描き、画面下部に荒野を、上部に広大な空を描く構図をとっており、ここにはある種の類型化が見られる。このことからも、曽宮にとって、毛無山はいわばライフワークの一つであったことが伺える。

図1 曽宮一念《毛無連峯》
昭和45年(1970)
キャンヴァス・油彩
53.0×72.7cm 静岡県立美術館蔵

図2 曽宮一念《失題毛無山》
昭和45年(1970)
以降キャンヴァス・油彩
36×45cm 個人蔵
(筆者撮影)
2.風景画と「想像画」について
曽宮は、風景画制作について、師藤島武二とのエピソードを交えながら、つぎのように述べている。
「また、「僕は風景画が好きでよく描きますよ」っていう話をそこでしたら、「風景画っていうものは主に想像画だよ」って言われて帰ってきたんです。しばらくしてその次に行ったとき、夕映えの絵をおおいにぞんざいに描いて持っていったんです。そしたら藤島がそれを見て、「これは想像画じゃね」っていう。「先生がこの前、風景画は想像で描くものだっておっしゃったでしょ」って答えたら、先生は「だけど、それは五十すぎてからのことじゃよ」なんていうんだね。その時はせいぜい二十六、七歳だったけど、釘さされちゃったよ。」3
ここで言う「想像画」とは、目に見える風景をありのままに描くのではなく、それらを画家の「記憶」と重ね合わせて、主観性や装飾性、象徴性などを加味して再構成することを意味している。藤島に苦言を呈された若い曽宮は、以後、風景と真摯に向き合いながら、自らのリアリズムを追及していった。このエピソードは、曽宮の風景画に対する姿勢を示すものとして興味深い。
さて、こうした風景画における「想像画」、すなわち画家の「記憶」の問題は、多くの風景画を語る上で重要な問題である。例えば、セザンヌは生まれ育ったエクス=アン=プロバンスに聳える《サント・ヴィトワール山》連作を制作する際に、現場で見た風景に自らの「記憶」を重ね合わせて描いたし、また和田英作が後年、静岡県・三保にアトリエを構えて、制作し続けた《富士》も、現場での写生に画家の「記憶」が重なり合っていることは言うまでもない。和田英作が早朝に現場へ出かけ、山頂が赤く染まる富士を幾度となく捉え続けたのは、現場の生々しいリアリティーを得るためばかりではなく、自らの脳裏に富士の「記憶」を刻み込むためでもあった。4画家は、現場で見たありのままの風景に、それによって得られた「記憶」を重ね合わせて一つの作品を制作したのである。
3.曽宮の風景画に対する姿勢について
《失題 毛無山》は、曽宮の失明後、あるいは、ほとんど視力が皆無の状況で、制作されたと述べた。若い頃から、目の病に苦しめられてきた曽宮にとって、風景画を制作することは、「見ることとは何か」を問い続けることに他ならなかった。先に述べたように、現場で見た風景に画家の「記憶」を重ね合わせることで作り出される「想像画」が、曽宮の風景画に対する一つの姿勢であるとすれば、本作は、まさに「想像画」であるといえる。一方で、当館所蔵作品について、曽宮は生前「絶筆」であると述べている。筆者もこの言葉に異論を差し挟むつもりはない。しかしながら、絶筆とされた作品の制作後に、同じ主題の作品が制作されたことは、曽宮夕見氏の証言から明らかである。曽宮が当館所蔵作品を絶筆とした意図は、本作の完成度と目の状況の悪化によるものと考えられるが、その後同じ主題の作品を制作したことによって、曽宮の風景画に対する制作姿勢が明確になったのではないか。すなわち、風景画とは、現場で見たありのままの風景を捉えることだけでは成立せず、そこに画家の「記憶」を重ね合わせて作られるものであるという考え方である。視覚を絶対的な拠り所とする絵画という領域において、画家の「記憶」という、もう一つの感性の存在を示した曽宮は、絶筆という概念が、視力に依拠するのではなく、画家の制作意図にのみ従うものであることを示した。それゆえ、《毛無連峯》は、消えかけた視力と「記憶」とによって制作された絶筆というに相応しい作品であるとともに、《失題 毛無山》は、「もうひとつの絶筆」というべき作品である。
(たいいりょう
当館上席学芸員)
1 曽宮一念『画家は廃業』静岡新聞社 平成4年1月 193頁。下線は筆者。
2 同 125-126頁
3 同
4 拙稿「研究ノート 和田英作「富士」について」 静岡県立美術館ニュース「アマリリス」2002春 No.65 6-7頁
付記 本稿執筆に際して、曽宮夕見氏に貴重なお話を伺った。記して謝意を表する。