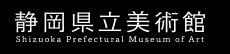![]()
研究ノート
「下村観山・横山大観《日・月蓬莱山図》— 主題と朦朧体との関わりについて」
森 充代

横山大観 〈月の出〉

下村観山 〈日の出〉
《日・月蓬莱山図》 絹本墨画淡彩 掛幅 静岡県立美術館蔵
本作は、蓬莱山を主題として、右幅「日の出」を下村観山、左幅「月の出」を横山大観が描いた対幅である。その展評において“朦朧体”という言葉が初出した、明治33年(1900)4月の第8回日本絵画協会・第3回日本美術院連合絵画共進会に出品されたもので、この作品によって観山は銀牌・二席を受章している。初期日本美術院を特徴づける新画風、朦朧体を軸に語られることの多い作品だが、この小論では蓬莱山という主題に着目し、そこから出発して朦朧体の意味について考えてみたい。
蓬莱山は、中国の神仙思想にもとづく霊山であり、渤海の東の海上にあって、仙人が住み、不老不死の薬があるという。吉祥図として描き継がれてきた伝統的な画題である。この蓬莱山について、岡倉天心がその考えを述べたものがある。日本美術院では、与えられた課題に対して各自が作品を持ち寄る研究会が、ほぼ月例で開催されており、明治33年11月の研究会における課題が「蓬莱」であった。蓬莱山図に期待することを、天心は次のように述べている。「蓬莱は古人の書きふるしたる図なれば、其上に新意を発揮せんとすること甚だ容易ならざることなるべし。されども、殊に本題を撰びたるものは、此容易ならざることの成功を望むに外ならず。」(註1)
蓬莱山という伝統的な主題であればこそ、新しい要素を盛り込むことが求められた。さらにいえば、新意を発揮すること自体が、蓬莱山図に取り組む際の主要課題だったのである。《日・月蓬莱山図》発表後の言葉ではあるが、天心のこうした考えは、大観・観山らも基本的に共有していたものと考えてよかろう。
では、本作において新意はどのような点に発揮されているのか。ひとつは現実感の導入、もうひとつは、その現実感と、主題が求める霊性やスケール感の両立という点に認められる。そして、その両方に朦朧体が寄与していると考えられる。
現実感については、特定モチーフの抑制、日・月による時間の表現、水平視の導入、そして朦朧体の活用によって表される。まず、蓬莱山の象徴である鶴はごく小さく描かれており、とりわけ観山は樹叢に羽を休める鶴を画面の隅へ隅へと寄せている。大観の方は最前列の岩上に霊亀を配するが、こちらも一見しただけでは見逃してしまうほどにさりげなく、小さく扱われる。蓬莱山を示す記号となるべきこれらのモチーフの抑制は、吉祥イメージに満ちた霊山という特質をも抑制しながら表現することになる。さらに、日・月の組み合わせは、天空を支配するものとして象徴的な役割や機能を託されることが多いが、ここでは、ほのぼのと明るくなり始めた曙、徐々に暮れ行き月が昇ってくる宵の口、というそれぞれ具体的な時刻の情景として表されている。日・月に実際の一日の時間の流れを当てはめている点で、その象徴性、超越性は弱まっているといえるだろう。蓬莱山本来の吉祥性や神聖さを抑制されることで、描かれた山は、神仙世界における非現実的なものではなく、山としての実在感、現実感を伴った存在として見えてくる。さらに、朦朧体によって三次元的な空間表現や立体感を取り入れることによって、現実感は一層強められる。観山は、海上に浮かぶ山、という蓬莱山の重要な要素さえ盛り込まず、朦朧体を用いた独特の陰影表現により、その立体感を表すことに主眼を置く。大観も、線描を排し、面的なもやもやとした色彩の変化で山の量塊感を表すことに苦心している。これらが、蓬莱山図に一般的な俯瞰視ではなく、ほぼ水平の視線から眺められることによって、さらに実際の視覚に近い印象を与えることになる。
蓬莱山という伝説上の霊山を、現実に存在するかのような、臨場感、実在感をもって表現することに心を砕いた構成といえよう。しかし、そうでありながら、ただの山になってしまっては意味がない。蓬莱山であるならば、霊山としての神聖さ、霊性を感じさせることが必須条件であるからだ。本作の場合、上述したように直接的な吉祥モチーフを抑制する一方、スケール感の強調や暗示的な描写の効果によって、蓬莱山の蓬莱山たるべき霊性の表出を試みている。
まず、画面寸法は各縦98.0cm、横154.0cmという大幅で、大型化が進んだ近代日本画の中でも、掛幅としては異例の大きさといってよい。その中に、蓬莱山は近接した視点から大きく描き出され、雄大な趣がよく表されている。モチーフが極めて限定的で、山の描写のみに集中したかのよう構成も、その壮大さを強調するものといえよう。また、波にしろ鶴にしろ、動きのあるものについてもその運動感は抑制されており、画面は静謐さに満ちる。その静けさと調和の中に、霊山の神聖さが託されるのである。さらに朦朧体の特質がここでも活用される。
朦朧体は、その最初期から常に批判の対象であったが、わずかながら評価された点が、その茫漠とした描写が呼び起こす感覚的な効果であった。「「イムプレッション」の或一面の現されて居る所とは感心する」「朦朧たる彩色やぼかしで、縹渺たる感情は面白く現されて居るのがある」(註2) これらの効果が、蓬莱山の神聖さの表現にうまく重ね合わせられているのである。朦朧体批判の根拠ともなった、描写の不明確さ、曖昧さ、そして全体の漠とした印象が、神仙世界の超俗性、曰く言い難い、人知で捉え難い霊性を暗示し、想起させるものとして効果を挙げているのである。
「大観と観山と対にかいた蓬莱の図があったが、何だか気味の悪い山で、一寸もおめでたくないには困る。殊に大観のが最も薄気味が悪い。観山の方は昼間の図だけあって少しは陽気じや。」(註3)
この「気味の悪い山」という評言は、大観・観山らが狙った効果のある一面に、敏感に反応したものといえるのではないだろうか。確かに、伝統的な蓬莱山図とは吉祥イメージに満ちたもののはずで、本作はその期待を裏切るものであったかもしれない。その代わり、主題本来のスケール感や霊性を強く押し出しつつ、現実感、実在感を織り交ぜていくことで、それまでにない新しい蓬莱山図を打ち出したのである。そしてそこには、朦朧体の特質がうまく生かされていた。線描を排して光や大気、空間を表しつつ、曖昧さや茫漠とした描写の暗示的な効果が超俗性を宿す、というその二面性の特質である。本作は、極めて東洋的な、伝統的な画題である蓬莱山を、この時代の彼らの新画風、朦朧体によって再解釈し、表現したものなのである。主題と描法が見事に一致し、この時期の彼らの目的にも合致した特殊な成功例といえるのではないだろうか。
(もり みちよ 当館学芸員)
註1 岡倉天心による水野年方作品への評言から抜粋 『日本美術』25号 明治33年12月
註2 「美術展覧会を評す」無名子 『東京日日新聞』 明治33年4月10日
註3 「美術展覧会を評す」(つゞき)無名子 『東京日日新聞』 明治33年4月18日