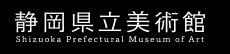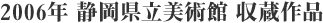![]()
ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ 1720-1778
ピラネージ20代初期の作品である。古代ローマの空想の納骨堂を、廃墟になった姿で描き出し、ここに崩壊した建築のモチーフやスフィンクス等を散りばめている。このような廃墟のモチーフは、既に当館に収蔵されているマルコ・リッチの≪神殿とゴシック聖堂のある廃墟の眺め≫のような作品からの影響だと思われる。本作品には、後年の圧倒的な迫力は無いものの、未だ将来の先行きも定かでない若き作者の、新鮮で震えるようなタッチを見て取ることが出来る。

《納骨堂》
1742年頃?
40.2×27.8cm
紙、エッチング
オーギュスト・ロダン 1840-1917
ロダンは、生涯に4種の本の挿絵を引き受けた。友人ミルボーの著作『拷問の庭』のために制作した挿絵は、その3番目にあたる。奔放な性の解放と常識的なモラルを打ち破った本の内容に沿って、ロダンは20点のデッサンを描き、それを元に版画家オーギュスト・クロがリトグラフを制作した。女性の裸体を自由に捉えたスタイルは、ロダン晩年のデッサンの特徴である。

《ミルボー作『拷問の庭』》
1902年刊行
32.2×24.5cmほか
紙、リトグラフ
飯田昭二 1927-(昭和2-)
鏡によるトリックを巧みに生かした作品。鳥かごの中央が両面鏡の平面で仕切られており、一方の空間には青いハイヒールの片方が、もう一方に白のハイヒールの片方が置かれている。左右一方からの像を見比べると見ると、青と白のそれぞれ同じ色の一組の靴が閉ざされた鳥かごの空間の中に置かれているかのように見える。鑑賞者はかたや実在する物体であり、かたや鏡に映った虚像である靴を同時に見るとき、対等に相立している実像と虚像の関係性に惑わされる。

《Half and Half》
1968(昭和43)年
48.4×50.0×50.1cm
鳥籠、靴、鏡
小池一誠 1940-(昭和15-)
1960代後半、石子順造をはじめとする当時の先鋭的な評論家や美術家の間で「表現とは何か」という問題意識が高まっていた。小池は、人間が石を素材にして主体的に造形物を作リ出すのではなく、人間も石と同じ世界の一部ととらえ、その人間が自然とどう関わりあえるかという意識に基づいて表現活動を行った。藁科川で見つけた大きな石を、まるで柔らかいかまぼこか何かであるかのように見事に切ってしまったこの作品もまた、作家が自然と関わりあった行為の痕跡であるといえる。

《No.1 石》
1969(昭和44)年
約130×約110×約40
(展示した状態で)
石
鈴木慶則 1936-(昭和11-)
 《非在のタブロー (マグリットによる)》 1967(昭和42)年 122.0×96.5×4.6cm キャンヴァス、油彩 左半分にはルネ・マグリットの絵画《人類》が、原物をわずかに違え、縦方向に大きくトリミングされて写されている。一方、右側にはスタンプや釘にいたるまで本物そっくりにキャンヴァスの裏側が描かれている。名画から原物の絵画的価値を剥ぎ取り、素(す)のイメージを露出させることに加え、展覧会場では決して表に出ることのないキャンヴァスの裏側を見せるアイロニーによって、固定化した絵画や展覧会の制度に疑問を投げかけている。 |
 《非在のタブロー(キリコによる)》 1967(昭和42)年 101.8×82.0×8.0cm イーゼル251.2×85.4cm キャンヴァス、油彩、木 写し取られたジョルジオ・デ・キリコの絵画《預言者》の図像イメージは、巧妙に現物とは図像の配置が違えられている。作家の仕掛けにより、本作品に向き合う鑑賞者は、原物のキリコの絵画の中で人物がイーゼルの上の黒板に向き合うように、現実空間に再現されたイーゼルと絵画とに対峙(たいじ)することになる。まるで絵画の中の虚構の空間が目の前に出現したかのような錯覚を覚え、虚像と実像の転倒に困惑させられるのである。 |
丹羽勝次 1931-(昭和6-)
人間の眼の錯覚を利用して、二次元のイメージを三次元の立体に見せかけた作品。表面に取り付けられた梱包用の紐によって、立体感はいっそう際出っている。丹羽は1968年から69年にかけて同様の箱をテーマにしたヴァリエーションを数点発表しているが、いずれも三次元空間を二次元化する技法である遠近法を逆用することによって、絵画のメカニズムそのものをあらわにした作品であるといえる。

《箱シリーズ '68》
1968(昭和43)年
148.5×92.0×5.0cm
プリント合板、縄
前田守一 1932-(昭和7-)
 《遠近のものさし(折り尺)》 1967(昭和42)年 65.7×493.0×3.8cm(広げた状態) プラスティック、塗料 平面上に虚構の空間を作りだす技法である遠近法を、ものさしに置き換えて、現実の空間に出現させたものである。ただし、ものさしに書き込まれた目盛りや数字は実体に基づくものではなく、イメージに過ぎない。近代西洋の世界観や絵画を象徴する遠近法を、ものさしという日常的な物に置き換えた点で美術を日常へと下降させようとする意識がうかがえると同時に、作品が示す不確かな目盛りや数字は、視覚がいかにあいまいかを提示している。 |
 《遠近のものさし》 1967(昭和42)年 89.0×139.3×2.9cm プラスティック、塗料 白いプラスティック素材で出来たこのものさしは、目盛りの数字が増えていくにしたがって、ものさしの幅と目盛りの幅とが次第に広がっている。一方のくるりと湾曲した部分から覗いている裏面にも、おなじく目盛りがふられているが、こちらは表面とは反対に、目盛りの数字が増えるにしたがってものさしの幅と目盛りの幅とが次第に狭まっている。作家の意識は、近代西洋の世界観や絵画を象徴する遠近法そのものを問題にすることにあり、それによって表現とは、絵画とは何かを問うている。 |