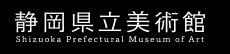![]()
研究ノート
前田守一 《遠近のものさし》に至る人的交流とその作品への影響
当館収蔵作品の前田守一の《遠近のものさし(折り尺)》(図1)、《遠近のものさし》(図2)は、どちらも1967年に制作された。ものさしとは、ものの長さを正確に測るための道具であり、目盛りの幅は均一であるはずのものだが、このものさしは、目盛りの間隔が次第に狭まり、外辺が消失点に向かって収斂する遠近法の線のごとく、1点で交わり、実際には四角のものさしの外形が、三角形で表されている。前田は、この作品で、3次元空間を2次元の平面上に表す遠近法の考え方を、ものさしの形状をした立体物で表現している。描くための技法である遠近法を、描かずに表現する行為は、描くことに対しての批評的振る舞いであり、西洋近代に成立した絵画という制度を相対化しようとした試みといえよう。遠近法という技法は、人間の目に錯覚をおこさせる、いわば視覚上のトリックであるが、この作品の、実際とは違うものさしの特異な形状や、正確ではない目盛りは、遠近法という仕掛けそのものを鮮やかに提示し、鑑賞者であるわれわれに、「見る」ことの曖昧さや視覚の騙されやすさを気付かせようとする。
前田は1967年に、同じタイトルで同様のコンセプトの作品を複数制作しており、上に挙げた2点のほかに残された作品や写真から6点は作られたことを確認する事ができる。

図1 前田守一
《遠近のものさし(折り尺)》 
図2 前田守一
《遠近のものさし》
ここでは、《遠近のものさし》以前の前田守一の足跡をたどってみたい。1932年に静岡県浜松市に生まれた前田は、1953年に静岡を拠点に活動する版画家の山口源に出会い、版画制作をはじめている。1959年、27歳の時、第27回日本版画協会賞、モダンアート協会展で新人賞を受賞し、版画家としての順調なスタートを切った。この時に制作された《作品CB-1 暗偶》、《作品CB-2 木偶》は、日本の伝統的な技法である木版画の質感を生かしながらも、幾何学的形態が組み合わされた現代感覚あふれる平面表現であり、戦後の前衛的な版画表現に一石を投じた作品といえる。なぜ版画家としてのキャリアを順調にたどっていた前田が、それから8年後の1967年に、版画作品とはまったく性質が異なる《遠近のものさし》シリーズを制作するに至ったのだろうか。《遠近のものさし》制作へいたるプロセスの中で、とりわけ重要な要因として注目すべき事は、前田が、1956年に後に美術評論家の石子順造として活躍することになる木村泰典と出会い、1958年石子(「グループ白」では木村卓の名称で活動)や鈴木慶則らとともに「グループ白(しろ)」を結成、1966年にはグループ「触(しょく)」のメンバーと合流してグループ「幻触(げんしょく)」を結成し、版画制作と並行して、版画という媒体にとどまらない最前衛の場に身を置いて表現活動に取り組んだ点であろう。
前田が参加した「グループ白」とはどのような会であったのか。1959年3月に刊行された「きかんし グループ白 No.3―グループ結成一周年記念号」に記載された「グループ白」の発会趣意書にはこうある。「芸術に於ける創造、批評、享受は常に正三角形の三角点として考えられねばならぬ。したがって、このグループの形成は、又自主的にマスコミ的集団化、個性の標準型的圧縮化に抗する創造的にして個性的な想像力の回復の指向である。グループ展、合評、講演、座談、研究会等、多角的にして有効な刺戟の糧を相互に再生産していこうではないか。」ここでは、創造、批評、享受とを相互関連性を持った活動と捉える姿勢が表明され、「個性的な想像力の回復」のためのグループ展、合評、講演、座談、研究会等のグループ活動を行っていく方針が明記されている。先に挙げた「きかんし グループ白 No.3」の記述によると、「グループ白」は1957年末に石子順造を囲んで集まった若い作家達が中心となり1958年2月に池田竜雄(龍雄)を招いた研究会の直後に発足した。この年には、毎月研究会が行われ、9月には「グループ白」が「清水絵の会」と合同で主催する「アンデパンダン静岡」展(会場:清水市青少年会館)が開催され、針生一郎と桂川寛による講演会が催されるなど活発な活動が行われている。またシリーズ展として1958年に前田守一、早川実版画展(戸田書店画廊)、1959年に伊藤隆史、早川実二人展(幸文堂画廊)が開かれたほか、1959年には2度のグループ展が開催され、1958年〜59年の2年間に3冊の機関誌が発行されている。
1959年、第27回日本版画協会賞、モダンアート協会展で新人賞を受賞し版画家としての活動にまい進していたまさに同時期に、前田は「グループ白」の活動に参画した。「きかんし グループ白 No.3」の中に、石子順造(木村卓)が前田に向けて書いた興味深い文章「絵画の純粋さについての疑問点−前田守一君へ−」が掲載されている。高い技術力を備える静岡の版画家の前田に、石子はどのような問題提起をしたのだろうか。
A4版2段組み8枚にわたる長文の中で石子は「グループの中でも高度な技術を身につけたすぐれた先輩の一人」である前田に向けて、「ただ技術的に(中略)いくら練達してみても、自己閉鎖的な職人的腕達者になる事はありえても、新しい価値を発見し創造して提示してみせると言う、その意味で新たなリアリティの附加価値行為でもある創造家は生まれはしないでしょう。」と述べ、この当時の前田の作風が、数年間のうちに、きびしい「純粋さ」の追求、「無駄の排除」の過程で着実に造形的密度の高まりをみせながらも、「具体性」を失いつつあることを危惧する指摘をしている。この文章の背景には、石子と前田や周辺の作家間で日ごろ交わされていた「絵画の純粋さ」、すなわち「作画上の無駄を一切はぶく」という場合の「無駄」とは何かという議論が前提としてあった。石子の文中の記述から、当時の前田は絵画におけるテーマ性、物語性、文学性の排除を問題にしていたようだが、石子は、我々人間の内部が外部とは無関係ではありえないため、絵画の「純粋さ」を「自律的な絶対性」にのみ求める前田の方向性は、合理的な単純化と密度の高度化にはつながりはするが、現代における芸術としての絵画には向かっていかないと鋭く批評している。この長文で石子が前田に突きつけた課題は、「より切実な(中略)我々の内部のあるリアリティを、視覚的に最小の絵画的言語要素を以って二次元の平面に新たな、間違いなくこれも実在する「もの」として定着し再提出すること」であると要約できよう(下線筆者)。石子は前田に「現代における芸術としての絵画」の問題に目を開かせようと熱く語りかけている。この石子の文章に対する返信のなかで前田は、石子の批評に対しての素朴な戸惑いとともに「芸術とは何か、何故描くのだとねじ込まれるとまいっちまう。(中略)何故描くのだなどと考えてみたこともない。」と述べている。版画制作を続けながら前田が、三次元の作品を発表したのは、7年後の1966年7月の「幻触」展(銀座・ギャラリー創苑)であった。この年9月には、「グループ幻触」主催の講演会で「美術に於ける現代とは何か」のテーマで、作家の高松次郎が静岡に招かれ講演を行っている。描くこと、見ることを相対化した作品《遠近のものさし》シリーズは、当時、遠近法をテーマにした作品を制作していた高松次郎の影響を指摘することは容易ではあるが、むしろそれ以前からの石子順造や、その周辺に集った仲間らとの足掛け10年に及ぶ「多角的にして有効な刺戟」を糧に花開いた、前衛作家前田守一の創造行為の成果であったととらえることができるのではないだろうか。
(当館上席学芸員 川谷承子)