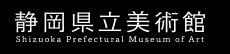![]()
研究ノート 「若冲の手紙」 福士 雄也
若冲の書いた手紙が残っていた—いや、正確にはその写真が残っていた、ということなのだが—これは衝撃的なニュースであった。若冲にまつわる同時代の伝記資料としては、大典による『小雲棲稿』所載の「藤景和画記」をはじめいくつかは存在するが、研究者の努力により存在が確認されているほかの同時代資料も全て第三者による記述であって、しかもその量は決して多いとはいえないのが現状である。同じ江戸中期の画家である円山応挙に関しては自筆書簡をはじめとする資料が多く残っているのに比べれば、雲泥の差である。そこへ、思いがけず若冲自筆の手紙が残っていたというのだから、これが驚かずにいられるだろうか。
件の手紙は、ごく最近発行された出版物に載る1。狩野博幸氏によれば、この写真乾板は長らく京都国立博物館に保管されてきたものというが、世に紹介されたのは筆者の知る限りこれが初めてであろう。若冲の肉声を伝える、まさに唯一無二の資料である2。当然その内容について気になるところだが、掲載書では「時候の挨拶」と触れるのみである。そこで、この機会に手紙の内容について若干の紹介をしておきたい。ただし、現時点ではその手紙の全文を解読しえたわけではない。機会があれば全文の翻刻やそれを受けての詳細な内容の検討についても改めて行うことができればと考えているが、ここではひとまず部分的な紹介をしておこう。
まず、全体のおおまかな主旨は、掲載書にもいうように時候の挨拶である。「残暑」ということばが3回登場し、「今年は頗る残暑も升升つよくこまり入り候」あるいは「をりをり残暑もつよく」などと繰り返し述べている。手紙の日付は「七月十九日」。これは旧暦であるから、現在で言うところの8月末にあたる。また、旧暦の七月は初秋ということになるから、夏も終わったというのに今年の京都はいつまでも暑い、というのであろう。それほど長文の手紙というわけでもなく、その中で3回も残暑について述べるところからみても、何か差し迫った事柄についての連絡でないことは確かだろう。
では、ほかに内容に見るべきものがないかというと、興味深いことばがいくつか見受けられる。まず、「画料」ということば。これはいうまでもなく画の料金ということであるから、若冲の仕事に対する報酬と考えられる。また、別の部分では「此度あふむ画・・早速差上申候」と述べている。若冲といえば鶏を生涯描き続けたことで知られるが、鸚鵡の絵もいくつか描いている。《動植彩絵》(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)のうちの《老松鸚鵡図》をはじめ、和歌山・草堂寺の《鸚鵡図》など着色のものもあれば、水墨で描くものもある。「差上」とあるから、この「あふむ画」は注文されたものではない可能性もあるが、「画料」について述べていることから考えても、この手紙の相手は若冲の顧客であったとも考えられる。
その手紙の相手であるが、宛名には「岡田仁左衛門様」とある。この人物が何者であるかは現在のところ不明であるが、文中に「素麺」の文字がみえる。若冲の素麺好きは、大典の書簡集『小雲棲手簡』により知られるところ。同書簡集からは、混沌社の詩人、岡君章から送られた御中元の素麺を若冲が大典とともに賞味したことが分かるが、このとき素麺好きの若冲は、大典の前で御中元の箱を抱え込んで独り占めするような仕草をしてみせたという。若冲の手紙の文面からは、どうやら岡田仁左衛門なる人物から素麺を送られたように思われるが、あるいは、この人物も若冲の素麺好きを知っていたのかもしれない。
もうひとつ、この手紙には人物らしき同じ名前が三度登場する。人名らしい、というのは、この何某が「・・差上申候画料何某より・・」、「あふむ画・・何某方より・・」あるいは「・・何某と・・罷り度・・」といったかたちで登場するからである。残念ながら前後の文脈が掴み切れずなんとも消化不良の感が強いところだが、岡田仁左衛門なる人物とこの何某の二人の人物について今後明らかになったあかつきには、若冲の交流関係について示す新たな資料として注目されるだろう。
本文の文末は、「恐々謹言」という非常に丁寧な言葉で結ばれている。文全体を通してもそうだが、この書簡からは若冲の礼儀正しい人柄がうかがえる。この点は掲載書で狩野氏も触れているとおりである。残念ながら日付には年号が入っていないので、いつごろの書簡であるかは不明といわざるをえない。署名には「若冲」の文字が草書体でしたためられるが、これほど崩した略筆の署名は絵画作品には見当たらないのではないだろうか。字体の近いものとしては、《瓢箪・牡丹図》(細見美術館蔵)のうち《瓢箪図》の署名がある。これは、《牡丹図》の賛者である黄檗僧無染浄善の没年から、明和元年(1764)以前の作と考えられている。とくに、「冲」の字の3画目をほとんど完全に省略する書き方は酷似する。ただ、「若」の字は崩し方は似ているが、草冠の部分を二筆で書くところは《瓢箪図》より省略がすすんでいる。また、若冲は晩年「米斗翁」あるいは「斗米庵」と作品に署名しており、晩年期の書体と比較ができないので、字体だけから年代を推測することは難しいように思われる。鸚鵡という画題も、草堂寺の《鸚鵡図》が《動植彩絵》以前の制作であることから比較的若い頃から描いていたことが知られ、書簡の年代を推定する材料とはなりえない。全文の詳細な検討と、人物との交流といった視点から今後考察されるべき問題である。
大典「藤景和画記」の、「居士、人と為り断断として它技無く、唯だ絵事、是を好み・・」といった記述のためか、一般的には人付き合いの悪い孤独なイメージによって若冲が捉えられることが多いように思われる。それだけでなく、そうした一種変わり者の画家イメージが先行して、作品そのものが鬱屈した内面の吐露として解釈されることもある。とりわけ、《動植彩絵》の《芦雁図》に代表されるような粘り気のある雪の表現や、鳳凰画の尾羽にみられるハート型の模様、あるいは《動植彩絵》の《菊花流水図》では菊というモチーフと奇妙な形をした岩の表現などを、性的イメージと結びつけようとすることは少なからず行われている。これには、若冲が肉食をせず妻帯もしないで僧のような生活をしていたと伝えられることにも関係しているのだろうが、いずれにしてもイメージばかりが先行して作品解釈を規定してしまうことには危険を感じる。
「奇想」の画家であった若冲は、いまや江戸絵画史のなかにいかに位置づけるかが模索されるべき時期に来ている、あるいは現に模索されている状況にあるにもかかわらず、画面の中に個人の特殊な性的嗜好のあらわれを指摘し、それをことさらに強調することは若冲研究にとっても幸福なこととは思えない。若冲にまつわる同時代資料は、数は多くないにせよおそらく今後も発見されるだろう。それらの資料、あるいは研究成果が積み上げられることにより、若冲という絵師が適切に語られていくことが重要だろう。若冲と中国絵画、さらには朝鮮絵画との関連を探ることは、まさにそのような史的位置付けへの試みとして重要である。
その意味でも、来年当館にて開催予定の「朝鮮王朝の絵画と日本」展3は意義深いものになるはずである。同展は朝鮮王朝の絵画の全貌を明らかにしようとするものだが、若冲はじめ日本の絵画との関連もトピックとなる。朝鮮絵画との関連は、若冲の研究に新たな局面をもたらすに違いない。
(ふくしゆうや 当館学芸員)
註1 狩野博幸ほか『異能の画家 伊藤若冲』新潮社 2008
註2 ここに取り上げる書簡のほかに、若冲が《動植彩絵》三十幅を寄進したときの「寄進状」(宮内庁三の丸尚蔵館蔵)が自筆の資料として知られる。