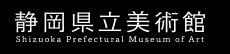![]()
研究ノート
他者/自己を見る目—ムーアによるロダン批評
南 美幸
それぞれ19世紀と20世紀を代表する彫刻家であるオーギュスト・ロダン(1840-1917)とヘンリー・ムーア(1898-1986)。生前ムーアは数多くの対談や文章による芸術批評を残したが、その中にはロダンに関するものも多い。ムーアが美術学校彫刻科に入学したのはロダンの没後間もなくだが、最初期にその影響を受けた作例があるだけで、後年、この偉大な彫刻家に対する賞賛は次第に大きくなったものの、直接の影響は受けなかったと、ムーア自身は述べている。しかし、ムーアのロダン批評を読み返してみると、2人の彫刻家には第一に人体を基本とする制作原理という共通基盤があること、翻って表現の関心と目的は異なることを、それぞれの作品を通してムーアがよく理解していたことが分かる。ムーアにロダンが影響を与えたのは、その表面的な形態よりもむしろ、人体への深い理解に裏打ちされた制作原理や哲学であった。
第一の共通基盤に関するキーワードは触覚である。ムーアは、批評家ロディティによるインタビューの中で、自らの「触覚の記憶」、言い換えれば「フォルムというものの概念に寄与してくれた少年時代の経験」について語っている(1)。学校から帰ると、リューマチを患っていた母の頼みでその背中をよくさすっていたのだが、その経験が後に円熟した女性の背中の表現に無意識に活かされたという。「触覚は彫刻の美的次元として重要」とムーアは主張するが、これは素材のもつテクスチャーや表面の仕上がりなどの触感をさすのではない。ムーアの「人体彫刻の歪みがもつ本質的に触覚的な性質」について問うロディティに対し、ムーアは「元来、視覚的歪曲よりも触覚的歪曲がある」のであり、「触覚の誇張した表現をもつ彫刻はますます刺激的になりうる」と答え、それを理解した彫刻家としてロダンの名を挙げている。ムーアによれば、「ロダンは彫刻が何たるかを知っていた。彼はかつて、彫刻とは隆起とくぼみのわざなのだと語った」。
ムーアが引用した先のロダンのフレーズは、モデリングすなわち肉づけという言葉に置き換えられる。「肉づけ。これは生命の反映である。生命そのものである」(2)と語るロダンにとって、それは立体造形の制作原理だった。コンスタンという職人から教えてもらった「形を広がりではなく、厚みで見る」方法を、ロダンは人体像の制作に応用した。
身体の様々な部分を多少なりとも平らな表面だとは考えず、内側のヴォリュームの突出として表した。胴体や四肢の膨らみごとに、その皮膚の奥深くにある筋肉や骨の発達を表現するようにした(3)。
加えてロダンの目的は、このようなモデリングの「理にかなった誇張の方法を見つけること」だった。結果、でき上がった作品は、鑑賞者の本能に響く触覚性を帯びることになる。
ロダンを偉大な彫刻家たらしめているのは、人体の内部構造に対する彼の完璧な理解、彫刻に内部を感じる彼の能力である。これは非常に強い。後期の作品さえ、その背後に、人体に関する他のあらゆる観察や知識を持っていた(4)。ロダンは身体に関して多くを教えてくれた。あらゆる視点からのアシンメトリー。堅苦しいシンメトリーを避ける方法。頭部、首、胸部、骨盤、膝などにおいて、身体のしなやかな部分はどこか。そして、これらの軸が互いに並行ではないこと。これらは像に生命力を与える方法なのだ(5)。
ロダンは基本的に塑像家であり、じか彫りに傾倒した時期があるように、ムーアは本質的に彫刻家という違いはあるものの、石やブロンズなど選択した素材、人体という中心モティーフは共通している。ロダンの中に自らと共通する制作原理を見て取ったムーアの作品には、独自のスタイルに昇華された、三次元性やヴォリューム、触覚などの造形的特質が現れている。
このような共通基盤とは対照的に、ムーアが明確に捉えたロダンとの差異がある。
大規模な完成作のみならず、トルソや晩年の即興的作品においても、ロダンは一貫して動きの表現を追及した。様々なダンスの動きを抽象的に捉えたロダン晩年の小像のシリーズ《ダンスのムーヴマン》を例に上げ、これらがドガの踊り子の作品と比較した場合、はるかに一瞬の動きを表現していることを、ムーアは認識している。しかし、この動きの表現は「私の世代がロダンに対する反動を表す方法の一つ」であり、次のように述べてムーアは袂を分かつのである。
私の彫刻では、物理的な運動の感覚で動きを把握することを探求しない。私は、あることが揺れ動き、構成され、硬直せず、呼吸する感じを与えることを追及する。マッスの配置によって、内部から伝わる動き、バランスが把握される。彫刻は動かないが、内部の運動可能性を持つ。それが私の好むものであり、ロダンを賞賛することに変わりはないものだ(6)。
主題における物語性や文学性の有無、抽象的形態への方向性などを別として、同じように人体をモティーフとしていても、ロダンとムーアを大きく隔てる造形的特質は、まさにこの点にある。
これまで引用したムーアによるロダン評は、1960年代から70年に集中している。1962年に開催された「知られざるロダン」展(ルーヴル美術館)は、現在ムードンのロダン美術館に収蔵されている石膏や断片の作品を公開展示することによって、再びロダンに関心が集まり始めるきっかけとなった。しかし、その後盛んに紹介されるようになるのは、80年代以降になってからである。そうした中で、ロダン研究者であるエルセンとの対話の中とはいえ、「ロダンは現代彫刻家の目を断片、スケッチ、偶然へと、そして無視されてきた古い彫刻の重要性へと開かせた」(7)というムーアの批評は、ロダンの本質を見抜いたものと言えよう。実際の作品のスタイルは大きく異なるものの、ムーアによるロダン批評からは、先達に対する彫刻家の透徹したまなざしが伺われる。
他者を通して自己を見つめ直す視点。ムーアの深いロダン理解は、自身の意識以上の影響があったからこそ、自作についてさらに掘り下げるきっかけの一つとなったのではないかと思われるのである。(みなみ みゆき 当館主任学芸員)
(1)以下、ロディティのインタビューの引用は全て次の文献による。
1960. RODITI, Edouard. Dialogues on art, Secker&Warburg, London, pp.179-188.
(2)1917. CLADEL, Judith. Rodin: the man and his art, with leaves from his notebook,
The Century Co., N.Y.
(3)1912. GSELL, Paul. Art: by Auguste Rodin, Hodder and Stoughton, London, p.60.
(4)1970. MOORE, Henry. <August Rodin: In conversation with Alan Bowness>,
Rodin : Sculpture and Drawings, Hayward Gallery, London, pp. 9-11.
(5)1967. ELSEN, Albert. <Rodin’s "Walking Man" as seen by Henry Moore: Albert Elsen in
collaboration with Henry Moore>, Studio International, no.890-891, pp.26-31.
(6)1967. MOORE, Henry. <Henry Moore parle de Rodin>, L'Oeil, no.155, Nov., pp.26-33.
(7)1967. ELSEN.