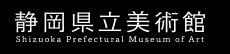![]()
研究ノート
川村清雄《巨岩海浜図》の寓意について(試論)
堀切正人

(図1)川村清雄《巨岩海浜図》
1912-26年頃(大正-昭和初期)
油彩、板 43.5×174.0cm 静岡県立美術館蔵

(図2)静岡県下田市、入田浜
2002(平成14)年5月撮影

(図3)川村清雄《巨岩海浜図》部分
静岡県立美術館所蔵の川村清雄作《巨岩海浜図》(図1)は、一見、海岸を描いた風景画のように見えるが、描かれている巨岩や人々は主題がはっきりせず、謎めいている。川村清雄が、日本近代洋画史において寓意画を描くことのできる特異な画家であったことを考えると、この作品についても、何らかの寓意が込められているのではなかろうか。
この作品の風景のもとになった場所は、静岡県下田市の入田浜と思われる(図2、注1)。巨岩のように見えるのは浜に突き出た崖の一部であり、実際には独立した岩ではない(現在はその崖をまたぐようにホテルが建っている)。川村清雄がこの場所を訪れて、実景をもとに制作したのか、あるいは写真などの何らかのイメージをもとにしたのかは不明であるが、崖の張り出した一部を、意図的に巨岩に見立て作画したものと考えられる。
この崖は、伊豆地方に点在する石丁場の一つであった。伊豆地方から切り出された石は、江戸時代、各地の城石として利用されたほか、幕末には外国船を砲撃するための台場建設にも用いられた。また運送途中で放棄された巨石も、伊豆地方の各地に今なお残っている。
図2右遠方にかすむ州佐利崎は、作品には描かれていない。あるいはその手前の狼煙崎とイメージを統合されたのだろうか。州佐利崎と狼煙崎は、その間に位置する下田港を守るための防衛線を形成し、幕末には両岬に台場が建設された(この防衛線を西へ伸ばしたところに入田浜の「巨岩」が位置する)。その台場建設に関わったのは、当時、幕府の勘定吟味役・浦々御備場御用取扱を務めた川村清兵衛(のちの修就)である(注2)。川村修就はその後、新潟奉行、長崎奉行、堺奉行などを歴任した幕府の高官であるが、川村清雄が敬愛したその祖父でもある。
《巨岩海浜図》の裏面には、紙片が貼りつけられており、「額 第六九号(厚様御遺物) 巨岩、海邊ノ図 川村清雄筆」との記述がある(なお、少なくとも昭和58年までは本作は「巨岩海辺図」と呼ばれていたが(注3)、当館収蔵後は、「巨岩海浜図」と呼称されている)。この貼り紙がいつ、誰によるか不明であるが、徳川家伝来の絵画によく似た貼り紙を見ることができる(注4)。「厚様」とは、徳川慶喜の四男で男爵だった徳川厚のことである(注5)。本作は、その旧蔵品であったか、少なくとも徳川家にゆらいするものと考えてよいであろう。
近年、那珂川町馬頭広重美術館、目黒区立美術館、江戸東京博物館などに川村清雄の作品、下絵、資料などが多数、収蔵された。その中には海辺を描いたものも多く含まれており、《巨岩海浜図》との比較考察が可能となった。それらには岩とともに、松(老木、巨木)、老夫婦、亀、あばら屋なども描かれる。海辺の松と老夫婦の図像は、熊手と箒との組み合わせも見られ、「高砂」であろう。となれば、一緒に描き込まれているその他のモチーフも、長寿や時の流れを補強するものと考えることができる。
岩や石については、江戸東京博物館所蔵の8点の資料が注目される。それは川村清雄が「君が代」の歌詞を繰り返し習練したものである(注6)。書き込まれているのはすべて「千代に八ちよに」以下の歌詞で、多くは「さざれ石乃いはほとなりて」を集中して書き記している。この下書きがいつ何のためのものかは不明であるが、川村清雄が石や岩のモチーフをどのようなものとして考えていたかを考察するには無視できない資料であろう。
長い年月をかけて、さざれ石が巌となる、あるいは逆に岩が砕けるというテーマの反映は、《巨岩海浜図》の油彩画法にも見て取れる。巨岩の表面に明瞭に残るパレットナイフのあとは、岩を刻みつけるかのようである一方で、巧みに絵の具を盛り上げている。浜の砂子をあらう波もナイフと筆を用いて、実に多様なマチエールを作っている(なお《波》(当館所蔵、葵文庫旧蔵)では、下地の黒い絵の具層を、意図的にパレットナイフで削り取り、その細かい剥落片を上から塗りこめる手法まで見られる)。また、川村清雄は神代杉を好んで用い、《巨岩海浜図》もその一例と思われる。地中に埋まったまま数千年を経た材木自体が、時の蓄積を示している(ちなみに伊豆地方は神代杉の産地である)。
巨岩が時の流れを象徴するものだとして、では、巨岩の周りの人たちは何を表わしているのだろうか。働く者、遊ぶ者、男、女、大人、子ども、着飾った者、粗野な身なりのものなど多様である。巨岩左の浜茶屋に腰かけた人たちは海を見ているが、一体、何を見ているのだろうか。江戸東京博物館などの浜辺の下絵類には、岬の形が《巨岩海浜図》と類似するものもあり、そのいくつかには鴉が描かれている。これはかつて勝海舟が所蔵していたと記録される《暁天鳴烏》と同じ主題であろう。だが《巨岩海浜図》には鴉も朝日も描かれていない。そもそもご来光を拝むために茶屋が立つような風習があったのだろうか。茶屋を設けるなら、月待ちかもしれないが、一般的な二十六夜月は、この方角からは出ない。描かれている場面の時代設定をもっと遡れば、黒船見物の可能性もあるだろうか。あるいは、類作《海浜祭礼図》(所在不明)では、浜に降りる神輿と大勢の見物人らしきものが描かれているが、《巨岩海浜図》には神輿はない。かりに祭礼の日としても、漁師と思われる労働者がいるのは不自然である。
《巨岩海浜図》の人物は、様々な連想を描きたてながら、特定の主題に集約されない。つまり、様々な人たちが様々な行為をしているということをのみ示す表象である。唯一、意味ありげなのは、茶屋に腰かけた人物の一人である。彼は海のほうを指差しているが(図3)、その対象は描かれていない。ただ、その方向は、岬の上の台場を結ぶ下田港防衛線と重なる。
《巨岩海浜図》の制作年は、サインの形状から推測すると、大正から昭和初期と思われる。この時代は徳川家にとって没落から復権への時代であった。その時点から振り返って、幕末から明治の動乱を経て、大正、昭和と変わった時代は、徳川家とその幕臣たちにとってどのように見えたであろうか。もし《巨岩海浜図》が徳川家のために描かれたものであったとするなら、開国の地、下田を舞台に、旭日を描くのでもなく、祭礼を描くのでもなく、ただ時の流れと平安に暮らす人々を描くことこそが、もっともふさわしい主題であったのかもしれない。
(ほりきり まさと 当館主任学芸員)
(注1)2002(平成14)年、川村清雄のご子息、故川村清衛氏から教示いただいた。
(注2)『下田市史 資料編三 幕末開港上』(平成2年)、小松重男『幕末遠国奉行の日記 御庭番川村修就の生涯』
(平成元年)参照。
(注3)川村清衛氏の展覧会礼状はがきによる。
(注4)徳川記念財団学芸員、柳田直美氏から教示いただいた。
(注5)(注1)に同じ。
(注6)江戸東京博物館、資料番号01001654〜01001661。
調査にあたっては、同館学芸員、落合則子氏に協力いただいた。