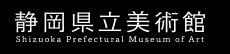![]()
研究ノート
「狩野派の世界2009」展余録 —戯画としての鍾馗図—
福士雄也
昨年秋、当館において開催された「狩野派の世界2009」展では、館蔵品を中心に65点の作品が出品された。館蔵品以外の出品作品については、展覧会にあわせて製作した図録1に図版と解説文を掲載したが、そこに1点だけ掲載されなかった作品がある。狩野山雪(1590−1651)による《鍾馗図》(図1)がそれである。展覧会開幕後に情報を頂いたため、会期後半に「特別出品」として展示することはできたが、図録に載せることができなかったのだ。そこで、この場を借りて作品に関する若干の考察を記述し、展覧会の余録としたい。
本作には、馬に乗った鍾馗が正面向きで描かれる。鍾馗とは、疫鬼を退け魔を除くとされる神のこと。玄宗皇帝(685−762)の夢の中に、進士試験に落第して自殺した鍾馗があらわれ、病を癒した故事に基づくという。快癒した玄宗が呉道子(680頃−750頃)に描かせたという鍾馗の図は、巨眼・多髯で黒冠をつけ、長靴を穿き、右手に剣を執り時に左手に小鬼を掴んだ姿であらわされることが多い。日本でも謡曲に取り入れられ、悪鬼調伏・国家守護の神として登場する。現在でも鍾馗像は五月幟に描かれ、また朱で描いたものは疱瘡(天然痘)除けになるとされる。古くは平安時代に制作された《辟邪絵》(奈良国立博物館蔵)にも描かれるなど、絵画化された例は枚挙に暇がないほどで、狩野派による作品も数多く遺る。
山雪に近いところでは、師山楽(1559−1635)による鍾馗図が複数知られているものの、意外なことに山雪による作例は管見の限り本作以外に見当たらない。その意味でも珍しい作例と言えるのだが、落款もまた珍しい。画面左下には、「狩野」白文楕円印に続き「山雪戯筆」とある(図2)。一般的には別段珍しい書き方ではないのだが、山雪にあっては他に類を見ない落款である。文字通り解釈すれば、戯れに筆を執ったということになる。実際、鍾馗を乗せた馬はどこか擬人化されたようなところがあり、その顔の表情などは実にユーモラスな雰囲気を醸し出しているから、「戯筆」とはこの辺りのことを言ったものだろうか。『本朝画史』の草稿執筆をはじめとする学究肌の気質や、作品にみる特異な形態感覚からは山雪のやや神経質な人物像が浮かび上がるが、このような作品も描いたとすれば大変面白い。
一方の鍾馗は、通例どおりのぎょろりとした眼、豊かな髯をたくわえ、長靴を穿いて右手に剣を持つ。それほど恐ろしい形相をしているわけではないが、肉太の力強い筆線によって輪郭された堂々たる体躯は神としての威厳を充分に備えており、その面貌表現は、晩年期の作とされる《蝦蟆・鉄拐図》(泉涌寺蔵)のうち《鉄拐図》に近い。ただし、本作が山雪の画業のどのあたりに位置付けられるかについてはいま少し検討が必要だろう。

図1 狩野山雪《鍾馗図》
紙本墨画個人蔵

図2 落款部分
ここで、改めて落款・印章に目を向けたい。先述したように、本作には「狩野」白文楕円印が捺される。この印を持つ作品は《盤谷図》(個人蔵)など数点が知られる程度で、使用例は少ない。印付の状態が良好ではないことから、両者の印影を比較検討することは難しいが、一応は本作も同印をもつ数少ない作例の一つに数えることができるだろう。もう一つの印は「蛇足軒」白文方印で、山雪の基準作に数えられる《達磨・龍虎図》(大通寺)にも捺される印章だが、磨滅の状況に応じてか作品によって印影も少しく変化を見せており、たとえば《出山釈迦図》(個人蔵)2 のそれと比較すると、同印かどうか俄かには判じ難いものがある。一方で、《仙人図貼交屏風》(東京藝術大学蔵)に捺される「蛇足軒」印とは印影が極めて近く、落款にある「山雪」の字体も酷似する。少なくとも、両者がかなり近い時期に制作されたと考えることはできそうだが、印影変化の問題についてはこの「蛇足軒」印だけでなく「狩野」印も含め、今後より多くのサンプルを集めたうえでの検討が必要になってくるだろう。
さて、先に述べたように、山雪による鍾馗図の作例は他に知られていないが、山楽の鍾馗図は複数の作例が知られており、それは霊験あらたかなものであったと林羅山の子鵞峰(1618−80)による『狩野永納家伝画軸序』は伝える。3よく知られるように、同資料中には山雪が常々語っていたこととして以下のような記述がある。すなわち、中国の故事を絵画化する際に原典に当たらず俗説に惑わされて図様を誤る者が少なくないので、実際はどうであるかというのを検討し、誤りを正して典拠に基づいた絵画制作を行うべきだ、というのである。このような山雪の作画姿勢を踏まえた上で、本作の図様を改めて見てみるとどうだろうか。すでに確認したように、本作の鍾馗は基本的には通例どおりの姿で描かれているのだが、馬に跨る鍾馗が被っているのは黒冠ではなく縁の広い笠のようなものである。このような姿は蘇東坡の載笠騎驢図を想起させるが、何か典拠があってのことだろうか。粉本としての性格を持つ英一蝶(1652−1724)《故事人物花鳥図巻》(個人蔵)中に鍾馗騎驢図があり4、他に虎に乗った姿で描かれることもあるが、これらについて何がしかの典拠があるかどうかは知らない。
そもそも、多くの鍾馗図がその図像的典拠とする冒頭の故事は、『後素説』にも引かれるように『事文類聚』5 の記事などによって「唐逸史」が伝える逸話とされているが、肝心の「唐逸史」なる史料そのものは伝わっていないようで、鍾馗の由来については古来様々に考証が行われている。いわく、神が椎つちで鬼を撃つという図像があったのを、椎のことを終葵とも呼ぶことから好事家が音の通じる鍾馗伝なるものをでっちあげた(『本草綱目』ほか)というものがあり、中山高陽(1717−80)も『畫譚鶏肋』の中でこの説を引いている。なお、『図画見聞誌』には呉道子による鍾馗図についての記述がある6 が、内容的に際立ったものはない。
問題は、このように原典のはっきりしない鍾馗の図像を描くに当たって、山雪が何を参照したかである。図像の前例踏襲や俗説を否定する山雪であれば、何か典拠とするものがあったと考えたいが、鍾馗と馬を結びつける根拠はよく分からない。同じように、山雪以外の作品で虎に乗った鍾馗図もあるがこれについてもその図像典拠は不明で、張天師の騎虎像に重ね合わされたとする説がある7。とするなら、本図も同じように東坡載笠騎驢図のイメージが重ね合わされたもので8、単に諧謔味を持たせたというだけでなくそのような図像典拠の曖昧さについての自覚を表明すべく、「戯筆」と表現したのかもしれない。
ところで、戯画として鍾馗を描くことはいつ頃から行われるようになったのだろうか。はっきりしたことは分からないのだが、18世紀以降では曽我蕭白(1730−81)が鬼に耳掻きをしてもらって恍惚の表情を浮かべる鍾馗を描いているし、河鍋暁斎(1831−89)も戯画としての鍾馗図を遺している。本作はこれらの作品ほど諧謔味や風刺性の強いものではないが、広い意味での戯画に含めることはできるだろう。
福士雄也 当館学芸員)