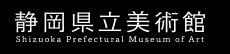![]()
研究ノート
橋本雅邦《三井寺》における先駆性について —描法と主題から—
石上充代
幕末期木挽町狩野家の高弟として名をなし、明治期は岡倉天心と共に日本画革新に取り組んだ橋本雅邦(天保6—明治41/1835—1908)。東京美術学校教授として横山大観、菱田春草らを育成した教育者でもあり、幕末から明治への大転換期に重要な役割を果たした画家である。静岡県立美術館が所蔵する《三井寺》にも、この時代特有の、また雅邦でなくては出来ない、独自の挑戦を見ることができる。描法、主題からそれを指摘してみたい。
本作は、明治27年(1894)4月10日から16日まで開催された「東京美術学校生徒成績物展覧会」において、教授による模範作のひとつとして出品されたものである。発表時のタイトルを「三井寺狂女図」といい、謡曲「三井寺」に取材しその主人公の女性を描いたものと分かる。
まず描法については、琳派風の表現が見られる点が注目される。衣を縁取る太くぼってりとした特徴的な描線や、緑、金、赤を取り合わせた明快な色づかい、色面の対比を際立たせる感覚などがそれである。このことは二つの点において意義深い。まずひとつは、近代における琳派再発見の先駆けをなすという点である。近代以降、画壇ではたびたび琳派風が流行するが、その第一波は明治後半期に起こった。明治30年代半ばから、西洋での琳派評価を逆輸入する形で宗達光琳に目が向けられるようになり、画家たちの間でも、例えば明治38年(1905)、欧米遊学から帰国した大観、春草が、論文「絵画について」1において、色彩重視の絵画を推し進める上で琳派研究に邁進すると述べている。実作品では、下村観山《木の間の秋》(明治40年)、菱田春草《落葉》(明治42年)、《黒き猫》(明治43年)などが琳派摂取の例としてしばしば挙げられる。《三井寺》はこれに先立つ明治27年の作であり、間もなく大きな潮流となる琳派風の先駆的な表現として重要である。
しかしながら、橋本雅邦にとって琳派とは"再発見"したものではなかった、という点が、本作における琳派風のふたつ目の意義である。大観、春草が"色的印象派"という言葉で宗達光琳を価値付けたように、彼らにとっての琳派とは、西洋との接触をきっかけとした伝統美術再評価の動向の中で新たに見出したものである。しかし、江戸末期の狩野派画塾で育った雅邦にとっての琳派は、そもそも同時代の研究対象として捉えられていたものであった。
元々漢画系の画派である狩野派だが、とりわけ幕末期にはやまと絵のみならず琳派あるいは浮世絵なども視野に入れ、画風を相当に変化させていたことが近年の狩野派研究の深まりの中で明らかになっている。雅邦が学んだ木挽町狩野家の先代・晴川院養信(寛政8—弘化3/1796—1846)は、膨大な数の古絵巻を模写し、やまと絵の画風を自らのものとして取り込み、洋風画法にも興味を示した。同時代の鍛冶橋狩野家第7代探信守道(天明5—天保6/1785—1835)もやまと絵に深く傾倒し、また初期風俗画の模写なども残している。その弟子にあたる鳥取藩御用絵師・沖一蛾は、狩野派に学びながら浮世絵、琳派、南蘋派、写生画などを取り入れ独自の画風を築いた。興味深いことに、雅邦の同門で画塾の二神足と並び称された狩野芳崖が、画塾のマンネリズムに我慢できず塾頭でありながら出奔、沖一蛾のもとへ走ったというまことしやかな話まである。雅邦が狩野派時代から琳派風の作品を残していたかは明らかでないが、琳派も含んだ幅広い作風に対して関心を持っていたと考えても無理はない。琳派風を先取りした《三井寺》であるが、その源泉は、幕末期狩野派の柔軟あるいは貪欲な絵画学習の中に発したものと考えられる。

橋本雅邦 《三井寺》
明治27年(1894)
紙本着色 130.5×64.0 掛幅 次に主題について。謡曲「三井寺」のストーリーは、我が子を誘拐され悲しみのあまり狂乱状態となった駿河国・清見関の女が、清水寺に参詣し、三井寺へ行くよう観音のお告げを受けるという前段、僧たちが月見をする三井寺境内に物狂いの女が登場、鐘が機縁となり、居合わせた少年が生き別れの我が子と判明するという後段から成る。本作では、ついに我が子に会えるかと三井寺の石段を必死で駆け上る母親が描かれる。赤子を胸に抱くように見えるのは、子の幻として衣の袖を抱きしめる錯乱した姿であろう。乱れた衣や切れた鼻緒、半開きの口元などからは、物狂いの女の尋常でない気配が漂う。頭を突き出した前のめりの姿勢や行く手を一心に見つめる眼差しからは、心急く様がひしひしと伝わってくる。宙を舞う瞬間を捉えた落ち葉の描写も、緊迫感を増す。母子再会というクライマックス直前の様子が、実に劇的に表現されている。
ところが、元々の謡曲の中にこのようなシーンは出てこない。本作で描かれたのは、雅邦が謡曲「三井寺」のストーリーを独自に解釈し、劇的な演出を加え、創作したものなのである。そこでは、和漢の文学的素養を盛り込んだ「三井寺」本来の格調高い趣や、鐘、月といった絵解き的な要素は排除され、狂気の母が夢のお告げにすがって石段を駆け上るという極めて具体的な一場面が選択された。そしてこの瞬間の母親の心理表現に、全てが注がれているのである。このように人物の感情、心理の表出を重視した点に、本作の主題面における先駆的な要素がある。画中人物の複雑で微妙な心理描写は、明治中期以降の歴史画に重要な要素となっていたことが指摘されている2 。この、彼らがいうところの"エキスプレッション" 3 重視の姿勢は、明治30年秋以降の批評において顕著になり、横山大観《聴法》(明治30年)、下村観山《継信最期》(同年)、小堀鞆音《恩賜の御衣》(明治31年)などがこうした観点で高い評価を得た。母親の心理、感情の表現を要として独自の解釈により構成された《三井寺》は、その点においても彼らを先取りしたものといえる。
以上、琳派風の描法や主題解釈、人物表現において、橋本雅邦《三井寺》が明治30年代以降顕著になる若手画家たちの作風の先駆的要素を備えていたことを確認した。明治27年という制作年を改めて眺めてみれば、還暦を迎えた橋本雅邦は東京美術学校日本画科の教授筆頭の地位にあるが、大観は前年、観山は同年卒業したばかりで、春草は未だ在学中である。次代を担う彼らは画家として発展途上の段階にあり、非凡な作品を残してはいるが、未だ生硬な、こなれない表現も多い。この時期、このような若手画家のごく身近な場所で、彼らに比して格段に優れた技術によって日本画の新潮流を体現することができた雅邦の存在は大きかったろう。彼が示した作風は、美術学校の学生らに強い印象を与えたはずである。模範作として出品されたことを考えれば、教育者としての雅邦の強い意気込みが込められたものともいえる。また、幕末期狩野派の創作意欲が幅広い画風の吸収を促し、それを基盤として雅邦の明治期の表現が可能になったのだとすると、狩野派の創造性、また近代以降の画家に与えた影響についても示唆するところが大きい。《三井寺》は、時代の転換点を生きた橋本雅邦ならではの独自のドラマを秘めた作品であり、前代と次代をつなぐ彼の仕事の意義をよく示すものといえる。
(いしがみみちよ当館主任学芸員)
(1) 横山大観・菱田春草「絵画について」1905 『日本美術院百年史』3巻下[資料編] 1992
(2) 塩谷純「小堀鞆音 恩師の御衣」『国華』1234号 1998、植田彩芳子「横山大観筆《聴法》制作背景としての
「エクスプレッション」—画中人物の感情表現をめぐって」『美学』225号 2006 等
(3) この場合画中人物の感情表現を指す。前注2 植田 2006